「太陽の塔って、いつ建てられたの?」「1970年の大阪万博って何だったの?」そんな疑問を持つあなたへ。本記事では、日本を代表するモニュメント「太陽の塔」の建設時期や万博での役割、保存の歴史、そして2025年大阪万博との関係までをわかりやすく解説。時代を超えて語り継がれる芸術の力を、一緒にひも解いていきましょう。
太陽の塔はいつ建てられたのか?建設時期と背景
建設期間は1969年〜1970年
太陽の塔が建てられたのは、1970年の大阪万博(日本万国博覧会)に向けた準備期間中です。建設が始まったのは1969年1月で、完成は1970年3月。わずか1年2ヶ月ほどで、あの巨大な構造物が完成しました。
当時としては非常に短い工期でありながら、直径20m、高さ70mを誇るインパクトあるフォルムが現実になったのは、まさに奇跡的なプロジェクトでした。
万博テーマ館としての誕生
太陽の塔は、1970年大阪万博のメインパビリオン「テーマ館」の中心に建てられました。テーマ館のテーマは「人類の進歩と調和」。その核となる象徴として芸術家・岡本太郎氏が依頼され、構想・設計・デザインのすべてを担当しました。
塔自体が「時間の象徴」とされており、過去・現在・未来を表す3つの顔を持っています。
建設を支えた技術と職人たち
建設には、延べ10万人以上の職人・技術者が関わりました。内部には鉄骨構造が張り巡らされており、現在の高層ビルと同等レベルの耐震性を備えています。外壁のうねりやアームの造形もすべてが手作業で仕上げられており、当時の技術力と芸術力の融合による産物と言えるでしょう。
また、構造設計は建築家・今井兼次氏や技術者・飯田益男氏らが手掛け、芸術と構造の融合に挑んだ前例のない試みとなりました。
岡本太郎が生んだ前代未聞の建築芸術
岡本太郎氏は、太陽の塔を単なるオブジェとしてではなく、「生きている存在」として捉えていました。そのため、塔は無機質な建築物ではなく、生命力を宿したモニュメントとして表現されています。
彼の言葉「芸術は爆発だ!」という精神そのものが、この太陽の塔には宿っているのです。
建設当時の評価と注目
当時は「不気味」「理解不能」といった声も少なくありませんでしたが、完成後は話題が沸騰し、テレビ・新聞・雑誌で連日報道されました。結果的に太陽の塔は万博の象徴として広く認知されることとなり、「万博=太陽の塔」というイメージが日本中に定着しました。
太陽の塔が公開されたのはいつ?万博での展示と役割
万博期間中の展示内容とは
1970年の大阪万博は、同年4月から10月まで開催されました。太陽の塔はこの期間中、中央のテーマ館として、会場のほぼ中心に位置して来場者を出迎えました。
外から見るだけでなく、中に入って鑑賞できる展示としても設計されており、塔の中には高さ40メートルに及ぶ「生命の樹」が立ち上がっていました。これは進化の過程を表すオブジェで、原始の海から人間へと至る命の流れを視覚的に表現しています。
中央テーマ館としての太陽の塔
太陽の塔は、巨大なテーマ館ドームの中心から突き出る形で構築されました。実際には屋根を貫通して外部に姿を現していたのです。この大胆な構造は、当時としては革命的であり、「展示建築としての新しいスタイル」を示したものでもありました。
内部構造「生命の樹」とは?
塔の内部に立つ「生命の樹」は、高さ41メートルに達し、幹には恐竜、哺乳類、霊長類など進化の系統を示す生物の模型が飾られていました。見学者は螺旋階段を上がりながら、生命の進化を追体験できる構造になっていました。
この内部展示こそが、岡本太郎が本当に伝えたかった「生命と時間の流れ」のメッセージです。
見学者数と当時の評判
万博期間中、太陽の塔を含むテーマ館は約1,200万人が訪れ、長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした。特に子どもたちや学生にとっては、普段見られない壮大な芸術と科学が融合した空間として、記憶に残る体験となったようです。
太陽の塔が象徴になった理由
単なる展示物を超えたメッセージ性、独創的なビジュアル、そして圧倒的な存在感。この3つの要素が融合し、太陽の塔は一躍「大阪万博の象徴」として君臨することになりました。今なお語り継がれる理由がそこにあります。
万博終了後、太陽の塔はどうなった?
一時は解体の危機に?
1970年の大阪万博終了後、パビリオンの多くは役割を終えて解体されました。実は、太陽の塔も当初は**「期間限定の展示物」**として、万博終了後に撤去される予定だったのです。
しかし、一般市民からの保存を望む声や、芸術的価値の高さが評価され、1975年には大阪府議会によって「永久保存」が正式に決定されました。まさに“奇跡的な生還”を果たした文化財です。
永久保存の決定とその理由
永久保存が決まった背景には、太陽の塔が大阪のシンボルとなり得るほどの強い印象を人々に与えていたことが挙げられます。岡本太郎氏本人も、保存運動に対して肯定的で、「これは時代の象徴として生き続けるべきだ」と語っていた記録も残っています。
加えて、塔の構造がしっかりと設計されており、再利用や保存にも耐えうると判断されたことも保存の後押しになりました。
劣化と保存問題
その後、長年にわたり風雨にさらされ続けた太陽の塔は、表面の塗装剥がれやひび割れなどの劣化が進行。内部は非公開のまま封鎖され、40年以上にわたり「閉じられた芸術」として眠ることになります。
特に2000年代初頭には、安全面の問題や建築基準の見直しも迫られ、大規模な修復プロジェクトが検討され始めました。
外壁修復と補強の歴史
2011年〜2018年にかけて、太陽の塔は大規模な保存修復工事に入りました。工事内容は、耐震補強、外壁の塗り直し、内部構造の再整備、生命の樹の復元など多岐にわたります。特に、岡本太郎氏が生前描いた設計図や記録資料をもとに、当時の雰囲気を忠実に再現したことが高く評価されています。
また、修復後の塔は文化財としてもより厳重に管理されるようになり、保護体制も強化されました。
現在の姿になるまでの道のり
2018年3月には、ついに太陽の塔の内部公開が再開され、多くの人々がその姿を再び目にすることができるようになりました。予約制による見学スタイルが導入され、1日あたりの入場者数を制限することで、安全性と鑑賞の質を確保しています。
今では、太陽の塔は「万博記念公園」のシンボルとして堂々とそびえ立ち、再び訪れた人々に感動を与える存在となっています。
太陽の塔の中に入れるのはいつから?
一般公開の再開は2018年から
長らく封鎖されていた太陽の塔の内部は、2018年3月19日からついに一般公開が再開されました。これは大規模な修復工事と安全対策が完了したことにより実現したもので、約48年ぶりに人々が内部に入れるようになった記念すべき瞬間でした。
このニュースは全国で大きな話題となり、公開初日は予約が殺到するなど、その人気は健在です。
内部見学の内容と流れ
見学は基本的に予約制で、30分ごとにグループ単位で案内されます。入場者は入口からエレベーターで中腹まで上がり、そこから「生命の樹」を囲むように設置された螺旋階段を歩きながら降りてくるという流れです。
進化の過程を表す生物模型や照明演出が施されており、まさに「芸術と科学の融合」を体感できる空間です。
チケット予約方法
見学には公式ウェブサイトからの事前予約が必要です。チケットは日時指定制で、週末や連休はすぐに埋まることが多いため、早めの予約がおすすめです。料金は大人720円(公園入園料別)とリーズナブルで、学生割引や団体割引も用意されています。
また、スマートフォンでのQRコードチケットにも対応しており、当日の入場もスムーズです。
内部の見どころ5選
- 生命の樹:高さ41m、進化の系譜を視覚化した塔内の主役。
- 照明演出:時間帯によって変化する光と音の演出。
- 螺旋通路:進化の流れを歩きながら体感できる構造。
- 岡本太郎直筆スケッチ展示:制作過程が垣間見える貴重な資料。
- 地下展示「地底の太陽」:復元された幻の展示物で、岡本ワールドの核心に触れられます。
見学の注意点と所要時間
見学時間は約30分〜40分程度で、ベビーカーや車椅子での入場は不可。また、内部は階段移動がメインなので、歩きやすい靴と服装が必須です。撮影は禁止されている箇所もあるため、公式ガイドの指示に従って見学を楽しみましょう。
これからの太陽の塔と2025年大阪万博との関係
万博記念公園の今とアクセス
太陽の塔がある「万博記念公園」は、現在も多くの人々に親しまれる大阪の人気スポットです。園内には、広大な芝生広場、日本庭園、国立民族学博物館などがあり、散歩やピクニックにもぴったりの場所です。
アクセスは、大阪モノレールの「万博記念公園駅」または「公園東口駅」から徒歩すぐ。2025年の大阪万博は夢洲(ゆめしま)で開催されますが、太陽の塔は引き続き「前回の万博の象徴」としての存在感を放ち続けています。
太陽の塔と2025年万博の“つながり”
2025年の万博では「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマが掲げられています。これは1970年の「人類の進歩と調和」と地続きの価値観であり、太陽の塔が体現した「生命の進化」「時間の流れ」とも深くつながります。
会場自体は離れた場所にありますが、大阪万博を語るうえで、太陽の塔の存在は外せない歴史的シンボル。2025年万博にあわせて、再び注目を集めることは間違いありません。
岡本太郎のメッセージと今
太陽の塔は、岡本太郎が「生命のエネルギー」を具現化しようとした芸術作品です。そのメッセージは、現代においても色あせることはありません。進歩とともに見失いがちな“いのちの根源”に目を向けるきっかけとなる作品です。
「芸術は爆発だ」という彼の言葉は、ただのキャッチフレーズではなく、今の時代を生きる私たちへの問いかけでもあるのです。
若い世代に伝えたい芸術の力
2025年の万博では、Z世代やミレニアル世代など、これまで太陽の塔を知らなかった層も多く訪れるでしょう。そんな若い世代にとって、太陽の塔は新鮮な驚きと発見の連続になるはずです。
ぜひこの機会に、1970年の万博遺産である太陽の塔に触れ、50年以上前の芸術が今なお伝えるメッセージを体感してほしいと思います。
次の世代への文化遺産として
太陽の塔は、単なるモニュメントではなく、日本の近代史と芸術を語るうえで欠かせない文化遺産です。これからも定期的な修復や活用を通じて、次世代へ受け継がれていくべきシンボルです。
2025年の大阪万博を訪れる際には、ぜひ少し足を延ばして太陽の塔も訪ねてみてください。50年の時を越えて、きっとあなたの心にも強く訴えかけてくれるはずです。
まとめ
太陽の塔はいつ建てられたのか?それは、1969年に着工され、1970年の大阪万博に合わせて完成した、高さ70メートルの巨大な芸術建築です。芸術家・岡本太郎が命を吹き込んだこの塔は、当時の人々に強烈なインパクトを与え、日本の万博史における象徴となりました。
万博終了後には解体の危機もありましたが、多くの人々の想いに支えられ、永久保存が決定。そして2018年には内部公開が再開され、新たな命を得て再び多くの人々に感動を届けています。
2025年の大阪万博をきっかけに、太陽の塔への関心はさらに高まることでしょう。半世紀以上前に作られたこの塔が、今も未来へと語りかけ続ける。太陽の塔には、そんな不思議な力があるのです。

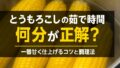

コメント